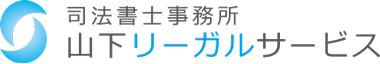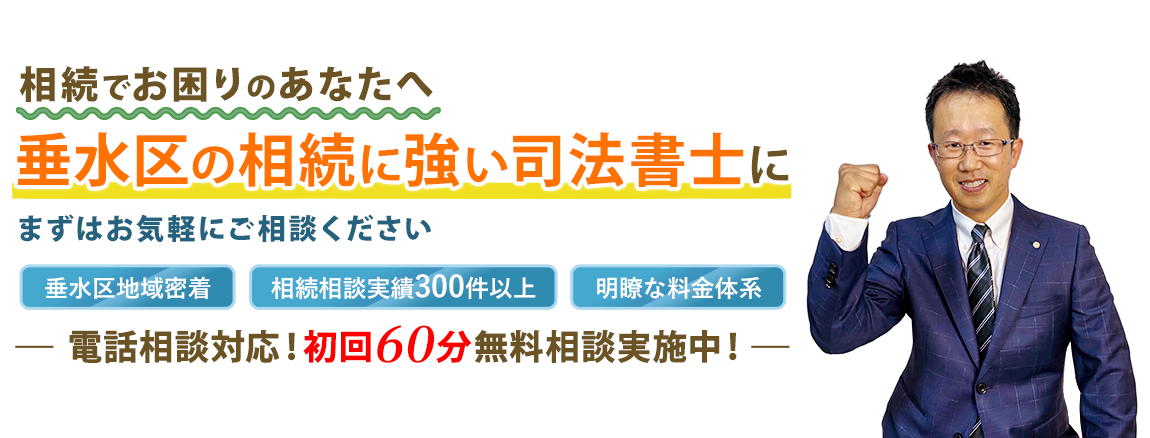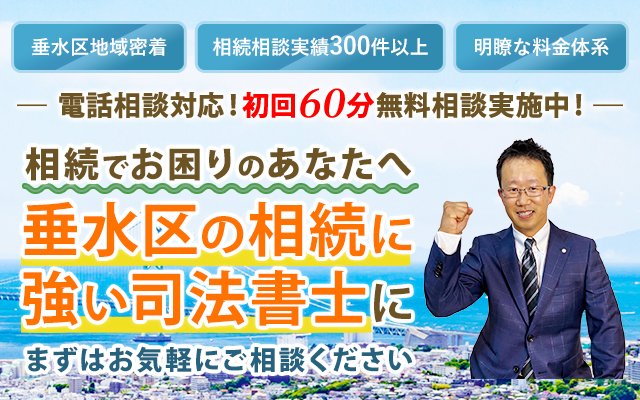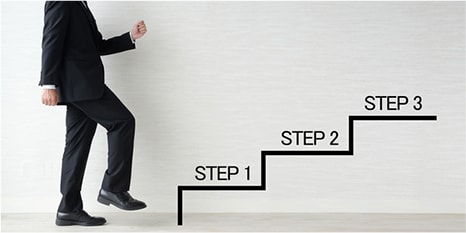お役立ちコラム
2022/09/08
円満な相続が結局はおとくな理由 相続税の「配偶者の税額軽減」

こんにちは、垂水、須磨、舞子、名谷の相続はおまかせ下さい。司法書士山下リーガルサービスの山下です。
今年2015年から相続税の基礎控除が大幅に下がって、これまでより多くの場面で相続税の課税対象になってくると思われます。
でも基礎控除を超える財産があったとしても配偶者大半の相続をした場合には「配偶者の税額軽減」により相続税はほとんどかかりません。
また一定の宅地を相続する場合は「小規模宅地等の特例」の適用があります。
しかし、上記2つの特例には申請の期限があって、相続手続きがもめて長引くとせっかくの減税措置が使えなくなってしまう恐れがあります。
相続税の「配偶者の税額軽減」を詳しく
配偶者は婚姻期間中に築いた財産は夫婦共有の財産であるという民法の考え方や、死別した配偶者の生活の安定のためという
理由で配偶者が相続する財産は特別な税額軽減制度があります。
これは、配偶者が遺産分割や遺贈で実際に受け取る財産が
「1億6000万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額」までなら配偶者には相続税がかからないという相続税の軽減制度です。
例えば相続財産が4億、相続人は妻と子1人だった場合、妻の法定相続分は2億なので2億までは相続税がかからなくなります。
しかし、ここで注意点があります。
相続税の「配偶者の税額軽減」が適用されるには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割を終え、相続税の申告書を提出する必要があるのです。
期限までに遺産分割がまとまらない場合は法定相続分で分割したとして計算した申告書を提出して納税が必要となります。
その際に必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するようにしてください。
その後3年以内に分割できれば、配偶者の税額軽減が適用でき払いすぎた税金は戻ってきます。
3年以内に分割できない場合はさらに適用期限の延長を申請する必要があります。
このように相続がスムーズに進まないと適用できない軽減措置があるため、相続は出来るだけ円満に進めたいものです。
次回は「小規模宅地等の特例」について解説します。